→書籍紹介:最新老化の科学がわかる本(3) →AGEs(糖化最終産物)(6)
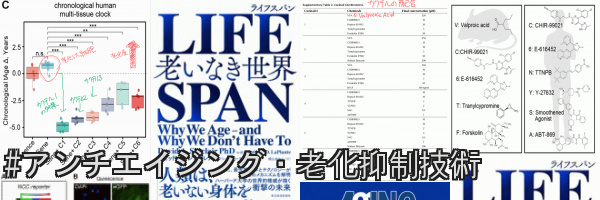
前のページへ|4ページ目/4|(1・2・3・4・)
1999.12.16長生きしたかったら。暇なときは目を閉じよう
1999.11.25遺伝子操作により哺乳類(マウス)の寿命を延ばすことに成功した
1999.10.22老化に伴って、ミトコンドリアDNAの中で細胞の増殖を司っている部分が損傷しているらしい
1999.02.28ヒトの細胞を人工的に不死化させることに成功した。
前のページへ|4ページ目/4|(1・2・3・4・)
1999.12.16 外界からの刺激を受け取れない線虫(C.elegans)の変異体は通常の線虫より2倍長生きする事が示された。
遺伝子操作により哺乳類(マウス)の寿命を延ばすことに成功した 今回、著者らはp66shcという。一種類の蛋白質の遺伝子を欠損させることでマウスの寿命を延ばすことに成功した。正常マウスの平均寿命が761日だったのに対して、p66shc欠損マウスは973日の平均寿命を持った。 人で言えば80歳の平均寿命が102歳になるようなものである。
老化に伴って、ミトコンドリアDNAの中で細胞の増殖を司っている部分が損傷しているらしい ミトコンドリアは細胞の中にあり、細胞が活動するエネルギーを生産する所である。 これまでに、マウスやラットなどげっ歯類の細胞を遺伝子導入することにより不死化することは可能であったが、ヒトの細胞は不可能だった。今回、著者らはこれまでの方法に加えて、テロメラーゼ遺伝子を導入することにより、ヒト細胞も不死化し無限増殖が可能になることをしめした。
著者らは、外界からの刺激を受け取れない11種類の変異体を作製した。daf-19欠損変異体(毛が無い)、体節が欠損(che-2,che-3,osm-1,osm-5,osm-6)。繊毛のある体節が異常(che-3,che-11,daf-10)などなど。。。。
通常の線虫の平均寿命が18.8日なのに対して、che-2欠損体では26.8日、che-3欠損体では、平均37.5日も生きた。
著者らは、これらにより、自然界では餌の入手しやすさや、線虫の個体密度などにより寿命がコントロールされているのだろうと言っている。
細く長く生きてもつまらんね。太く長く生きなくちゃ。
でも活動量が少ない方が長生きするのはよく知られている。例えば、肉体労働者より、頭脳労働者の方が平均寿命が長いそうだ。
ヘレンケラーは長生きしたっけ?
(Regulation of lifespan by sensory perception in Caenorthabditis elegans(Nature vol.42 p.804))
1999.11.25
生物の老化には、DNAについた傷が深く関わっている事が知られている。すなわちDNAについて傷の蓄積により老化が起こるというものである。p66shcは紫外線などの障害によりついた時に傷の修復回路のスイッチを入れる遺伝子である。すなわち、この遺伝子を欠損させることによりp66shcマウスはDNAの修復能力が常に高まっていると考えられる。
ん〜、なんとも言えないが寿命が延びると言うより、病気に対する耐性が強くなるって感じかな?DNAの傷のみで老化が起こるわけでは無いのでこの方法だけでは不完全だろう。
Nature 1999 vol.402 p.309
The p66shc adaptor protein controls oxidative stress response and life span in mammals
1999.10.22
今回、著者らはT414Gという変異について調べた(ミトコンドリア遺伝子の414番目がTからGへ変わる変異のこと)
65歳以上のヒトでは14人中8人にこの変異が起こっていたが、(57%)、若い人13人の中にはこの変異は見られなかった。
ミトコンドリアは体内で使用されるエネルギーを作る重要な組織だからな、老人がすぐ疲れたりするのはミトコンドリアが弱っているせいなのかな?
情報元:
Science 1999 vol.286 no.5440 p.774-779
Aging-dependent large accumulation of point mutations in the human mtDNA control region for replication
1999.02.28
細胞の不死化と、ガン化は紙一重なので、単に細胞をガンにしただけともとれる。しかし細胞を一時的にガン化させ、もとに戻すことが可能であるならば、移植置換用の細胞を得る良い方法となるのではないか
[1・2・3・4・]
Cation!!注意:このページには動物実験などで得られた研究段階の情報が含まれています。これらはなんら、人間に適用した時の効果を保証するものではなく、これらの情報を元にとった行動によりいかなる不利益を被っても管理人は一切責任を負いません。このページの話はあくまで「情報」としてとらえてください。


